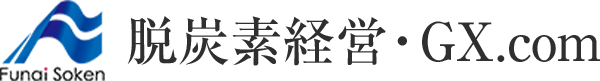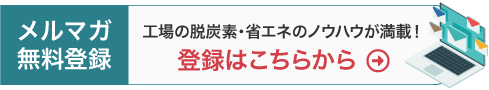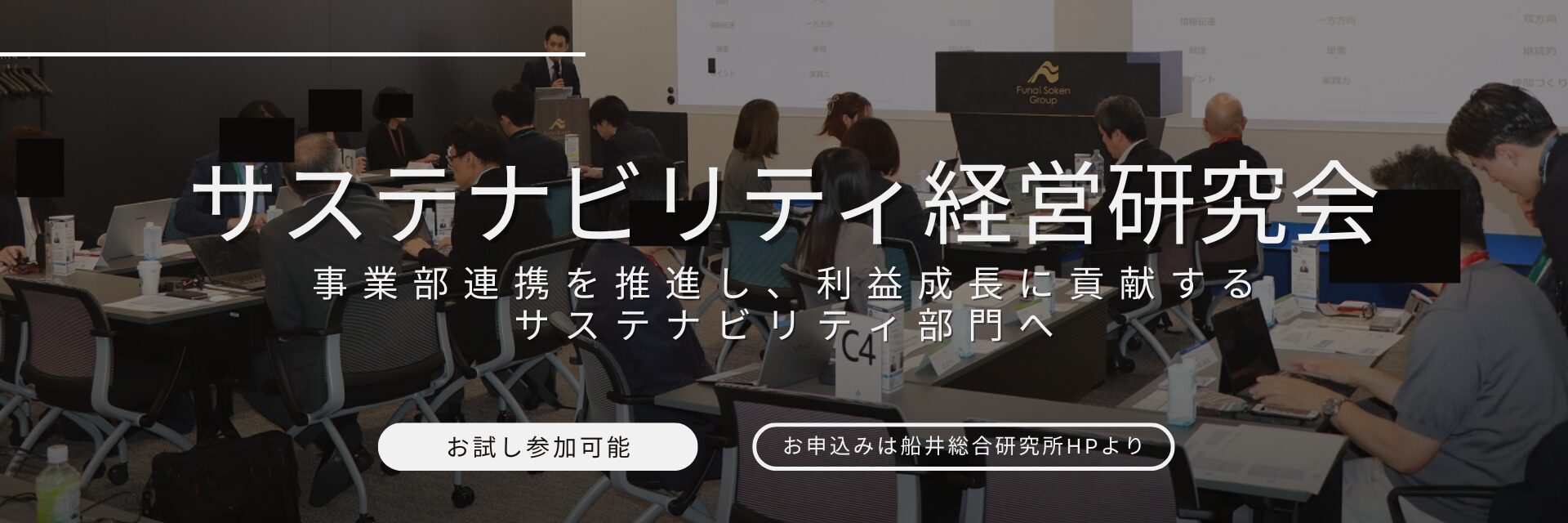サステナビリティ経営研究会 第一回例会「利益成長に貢献するサステナビリティ部門へ」
2025年4月23日に、サステナビリティ経営研究会の第一回例会が開催されました。立上げ例会となった当日は約30名のサステナビリティ推進部門責任者・実務担当の方にご参加いただきました。
このサステナビリティ経営研究会は「事業部連携を推進し、利益成長に貢献するサステナビリティ部門へ」という想いに共感頂いた仲間が集い、時流トレンドの紹介やモデル企業の講演、参加者同士のディスカッション・ネットワーキングを通じた気付きと学びを生み出す場となっています。

第一回例会のテーマ
―――――
利益成長に貢献するサステナビリティ部門になる
―――――
立上げ例会である当日は、本研究会の目指す姿である「利益成長に貢献するサステナビリティ部門になる」をテーマとして掲げ、進行していきました。サステナビリティ経営には3つの壁があると考えています。
業績優先の壁
・四半期の利益目標を優先し、長期投資が後回しになりがち。
・サステナビリティは重要でも、短期指標に埋もれやすい。
ROIの壁
・初期投資が大きく、いつリターンが得られるか不明瞭。
・経営陣を説得する根拠不足で、予算化が滞りやすくなる。v
役割の壁
・経営企画や事業部、サステナビリティ担当が別々のKPIを追いがち。
・責任範囲が曖昧で、連携や意思決定に余計な時間がかかる。
これらの壁を乗り越えることが、事業部との連携にあり、その結果利益成長に貢献するサステナビリティ部門になることができます。例会では、この壁とどのように向き合うかを講座・情報交換会を通してお伝えしていきました。
各講座のご紹介
第一講座 業成長を目的としたサステナビリティ推進の現在地
株式会社船井総研ホールディングス サステナビリティ推進室 シニアマネージャー 山路 祐一

―――――
船井総研ホールディングスのサステナビリティ推進責任者である山路からは、サステナビリティ部門の持つ役割を改めて定義することを発信しました。これは、サステナビリティ部門が直面している限界を認識しているためであると述べられています。具体的には、求められる情報開示が増加し、サステナビリティ部門が「非財務情報開示室」としての役割が主になりつつある現状を指摘しています。しかしながら、この状況に甘んじるべきではないとも強調されています。
サステナビリティ推進部門が保有する多くの情報は、本来非常に価値のあるものであり、それをいかにして企業の利益に繋げていくのかという点に、部門としてのこだわりを持つ必要があります。例えば、『開示』を『稼ぐ』ための戦略ツールと捉えることができれば、それは企業成長にとって有益な資産へと変化します。大切なのはサステナビリティ推進部門がどのようなマインドセットを持つかであり、その持ち方によって、これらの情報資産が単なる情報開示のためだけに活用されるのか、あるいは企業価値を高める有益なものとなるのかが決まってしまうとされています。
したがって、常に自身の役割を自問し、一つ一つの開示情報を自社の成長という文脈にどのように落とし込んでいくのかを検討し続けることが、極めて重要であると示しました。
第二講座 営業・事業部出身のESG推進室長が考えるサステナビリティ部門の在り姿
株式会社ニフコのESG推進室長 村田憲彦氏
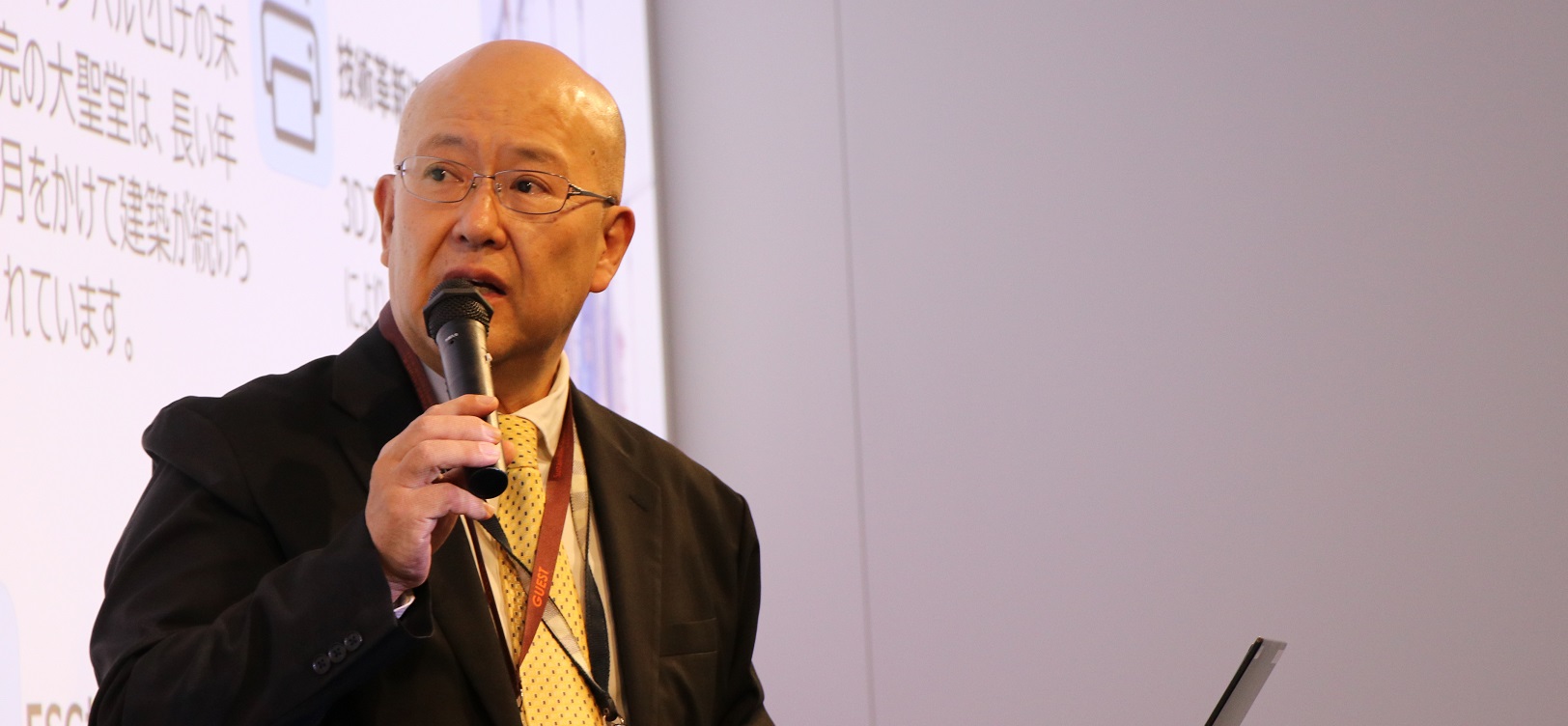
―――――
本講座では、同社が取り組んできたサステナビリティ活動の軌跡をご紹介いただきました。2021年にはESG推進室を設立され、MSCIを3年間で最高ランクのAAAに改善、さらには資源循環関連の業界横断的なプロジェクトを展開。自社のCO2排出量削減に限らず、サプライヤーエンゲージメントや⽣分解性プラスチックファスナー等の環境配慮製品の開発等、素晴らしい成果を上げていく中で、サステナビリティ部門がどのように各事業部と具体的な情報共有チャネルを構築し、共同目標設定を通じて社内意識改革を推進し、プロジェクトを成功に導いたかという点にフォーカスされました。
前提として、サステナビリティ部門の立ち位置を明確にすることが重要であるとしています。サステナビリティ推進は事業戦略そのものと位置づけられるべきであり、単なる環境活動や他部門の業務ではないとし、サステナビリティを推進するためには社内の意識改革が大切であると述べています。
そのためには、自社の目的を見極めること、そして事業戦略、財務戦略、ESGを構造体として可視化し、自社の経営においてサステナビリティがどのような役割・立ち位置を持つべきなのかという意識合わせを部内で行うことが必要です。その取り組みを通して見えてくることは、サステナビリティは将来の競争優位性の源泉を生み出す出発点であり、その視点をもって事業部に向き合うことで、「仲間」を増やす活動が成功の鍵となると指摘されています。
サステナビリティ推進部門をコストセンターとしてではなく、プロフィットセンター、あるいは競争優位性の源泉として捉え直すことが重要だと認識しています。小さな一歩から社内外の「仲間」と共に試行錯誤を重ね、自社の目的を明確にし、事業成長につながる形でサステナビリティを推進していくことが、サステナビリティ推進部門の役割であると結論付けています。
第三講座 なぜ、サステナビリティは社内浸透できないのか?
株式会社 船井総合研究所 カーボンニュートラルチーム ディレクター 貴船隆宣
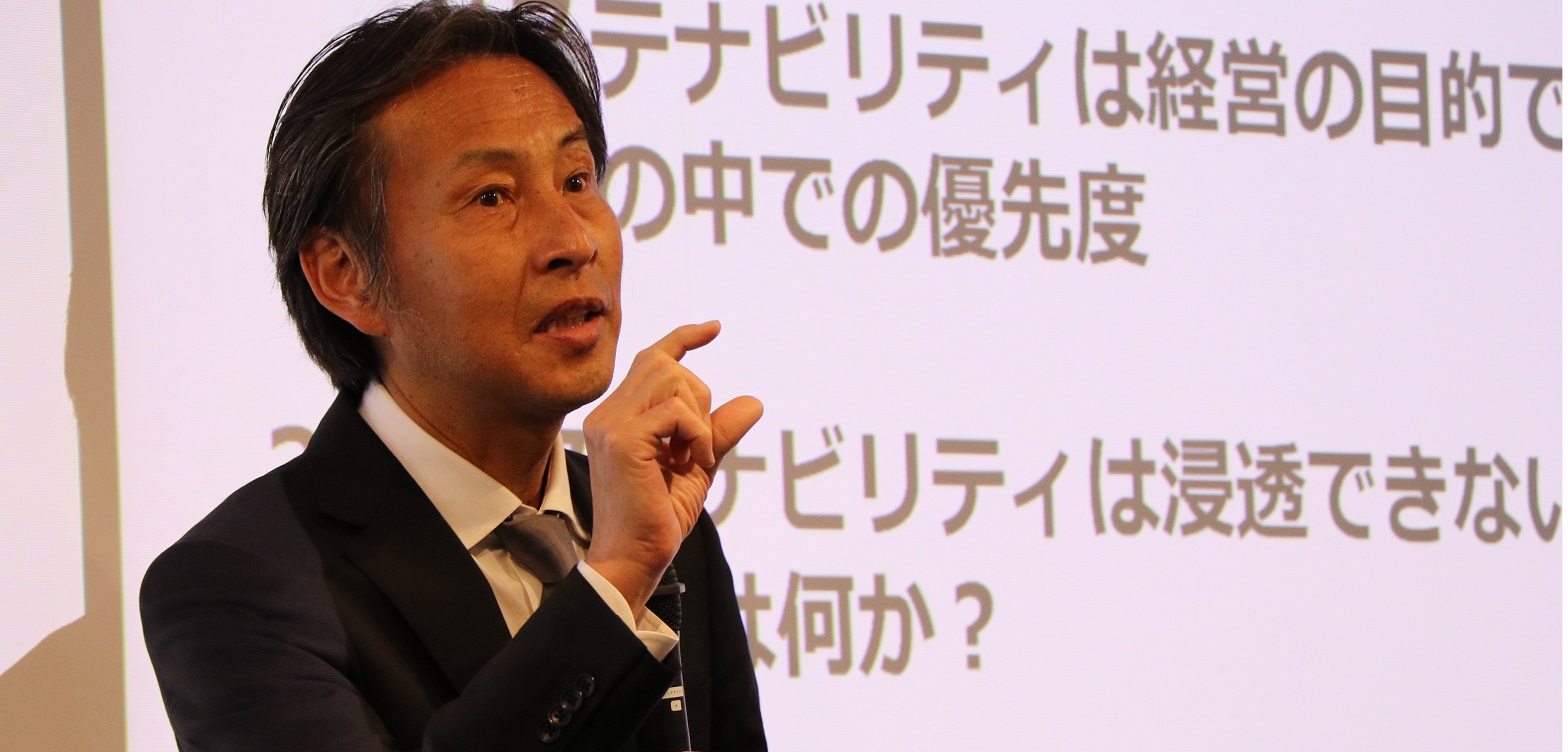
―――――
まとめ講座に位置する貴船の講座では、「社内浸透」という大きなテーマに対して、どのように向き合うかを述べています。現在のサステナビリティ市場は、外部からの要請と実際の市場ニーズが必ずしも合致しないという特徴的な環境にあります。このような状況下で、企業経営にサステナビリティを合理的に反映させることが、推進部門の主要な役割であると強調されています。
その上で、実態が伴う活動とするためには、事業部門との密接な連携と同時に、組織全体への「社内浸透」が不可欠であるとされています。しかし、「浸透ではなく共感」が重要であると提言しています。サステナビリティ部門が事業部門とどのように連携し、互いに共感し合いながら取り組むべきか、その時の向き合い方の重要性を述べています。
最後に、本研究会で得られることとして、共通の課題を持つ参加者が、それぞれの異なる分野で取り組んできた経験や知見を共有する貴重な機会であり、この場を最大限に活用し、新たな視点や解決策を見出してほしいと結んでいます。
参加企業様のお声
・今までもやもやしていた時に明確な答えをもらった気がします。取り組んで見て考えて良いと言うことは心強かったです。(建設業 現場推進役)
・「サステナビリティ経営」という大上段での切り口をテーマにした研究会は珍しいと思いますので、このようなテーマで議論できること自体が非常に良いと感じました。(製造業 現場推進役)
・複数の方からお話を聞くことで、社内だけでは生まれなかった発想を得ることができた(建設業)