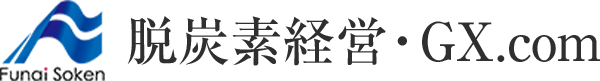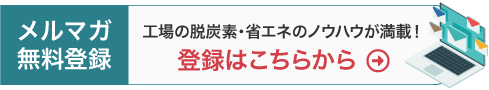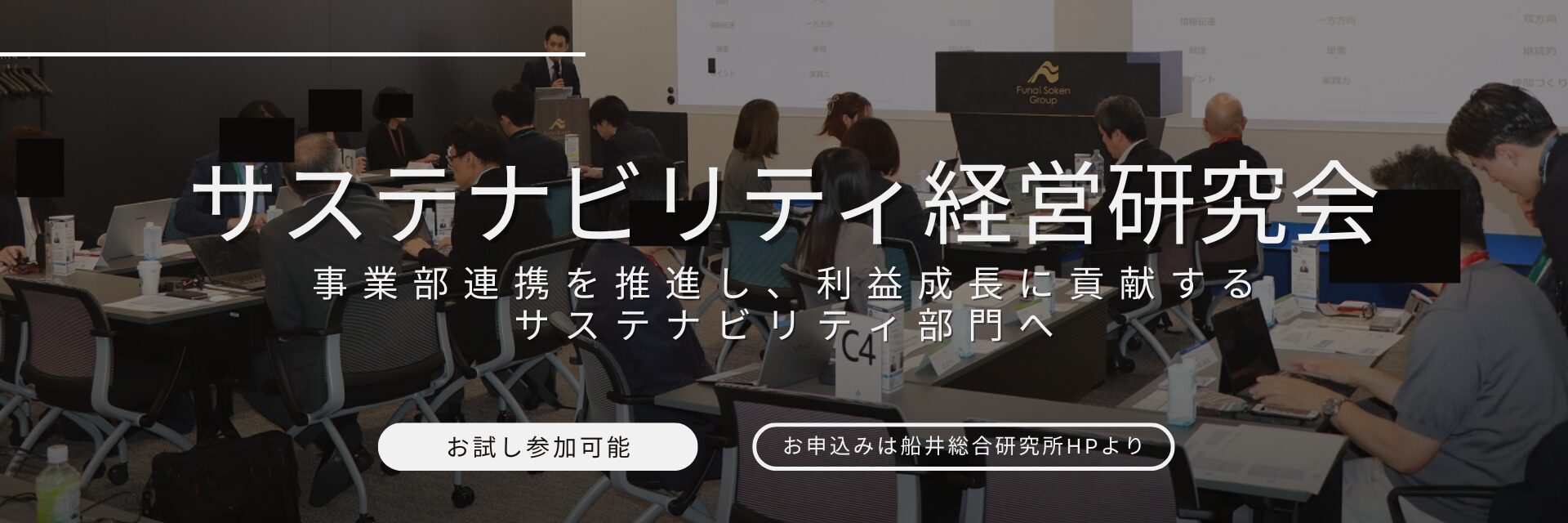サステナビリティ経営研究会 第三回例会「ボトムアップ型のサステナビリティ推進」
2025年8月8日に第三回サステナビリティ経営研究会が開催されました。
より実効性のある“サステナビリティ”が求められている中、その在り方について多くの議論が生まれています。特に本研究会の目指すべき姿である「事業部連携を推進し利益成長に貢献するサステナビリティ部門になる」という点においては、事業計画とサステナビリティの文脈の統合を図ることがポイントになります。
サステナビリティ経営研究会は、上場企業・同等規模のサステナビリティ推進責任者、推進担当者の方にお集まりいただき、上記のテーマについて議論する場です。専任部署の場合もあれば、事業部との兼任、経営企画や広報部門の一つの機能としてサステナビリティ推進を行っている場合もあります。それらは企業における考え方によるものですが、事業部との連携の必要性・利益貢献をするという点において、組織構成による変化はなく、共通の課題であるといえます。

第三回例会のテーマ
―――――
ボトムアップ型のサステナビリティ
①自社のサステナビリティ推進はボトムアップ型か?トップダウン型か?
②事例から学ぶ、これから取り組むボトムアップ型のサステナビリティ
―――――
第三回の例会では、「ボトムアップ型のサステナビリティ」をテーマとして設定しました。事業部との連携の在り方は多くのサステナビリティ推進部門の方の課題であるといえます。「もっと経営層が理解を示しリーダーシップを発揮してくれれば」「もっと現場が理解して、寄り添ってくれれば」という考えも多くありますが、その中で、サステナビリティ推進部門として何ができるのかを議論する場となりました。
各講座のご紹介
第一講座 ボトムアップでサステナビリティを推進する秘訣
株式会社船井総研ホールディングス サステナビリティ推進室 シニアマネージャー 山路 祐一、スペシャリスト 松永律子

―――――
第一講座では、講師である山路の経験を踏まえた、ボトムアップ型のサステナビリティの推進の在り方について発信しました。まず、前提として、トップダウン・経営陣によるリーダーシップを期待するためにも、最初はボトムアップ型、現場発信のサステナビリティが重要であると述べました。
その背景にあるのは、サステナビリティ部門が持つ「眠れるリソースの活用」の重要性です。サステナビリティ推進部門が集約してきたESGデータや、その取り組みは、昨今の時代情勢から顧客側においても求められる情報資産となっています。ただ、社内に蓄積された情報として扱うのではなく、事業部においても価値のある情報資産であるとし、その情報資産を起点としていきながら事業活動に関与していく流れを事例と共にお伝えしました。
また、船井総研ホールディングスにおいて、山路と共にサステナビリティ推進を担当している松永からは、事業部との連携を通してサステナビリティ推進の在り方がどのように変化していったのか、その様子を紹介しました。
講座後には、情報交換会・ディスカッションの時間が設けられ、自社のサステナビリティ経営がトップダウン型かボトムアップ型かの振返りを皆様にしていただきました。各企業の様子を見ていくと、推進の主体は現場側であることが大半であったように感じられます。
第二講座 理想と現実の狭間で掴む、ボトムアップ型サステナビリティ推進
LINEヤフー株式会社 執行役員 サステナビリティ推進統括本部長 西田 修一 氏

―――――
本例会のゲスト講演では、西田氏にLINEヤフー株式会社が取り組まれたボトムアップ型のサステナビリティの進め方についてご講演いただきました。講演では、CXOとの関わり方を明確にした組織体制を構築し、階層別研修を通してサステナビリティ施策の推進が認められる風土を作った事例が紹介されました。
第二講座後の情報交換会では、ゲスト講演の内容を踏まえ、自社においてどのような展開ができるかを検討し、共有していきました。
第三講座 研究会で目指すサステナビリティ部門の未来
株式会社 船井総合研究所 サステナビリティコンサルティングチーム ディレクター 貴船隆宣

―――――
第三講座では、当日のまとめとして「明日から事業部連携を進める為に」というテーマを掲げました。最初に挙げたことが「会社好き」な人の存在です。こうした会社好きな人というのは会社の発展においてポジティブな意見を持っており、そういった人と共にサステナビリティを推進させていくのが良いとしています。
また、事業部連携における重要な観点として、マテリアリティの重要性を挙げています。マテリアリティは事業面・社会環境面の二つの側面における共通項が設定されます。同時に、事業部側・サステナビリティ推進側の目指す方向性が一致している点であるといえます。その点をしっかりと見出す中で、中期経営計画とサステナビリティの一致を図っていく動きも重要であるとしました。
情報交換会の様子と参加企業様のお声



・ゲスト講演のお話は非常に共感できましたし、改めてスピードを上げて改革して行かなければと思いました(製造業 執行役員)
・できるところから少しずつ取り組みを行っていくこと。特に、既に着手している社内浸透関係については、サステナに興味のありそうな社員から徐々に声がけ等を実践できるといいと思った。(建設業 主任級)
・サステナビリティ推進をボトムアップで行う意義について改めて考えるよい機会になりました。ご紹介いただいた事例も事業を起点とした考え方で、刺激を受けました。(製造業 マネージャー職)