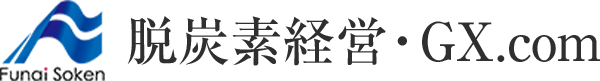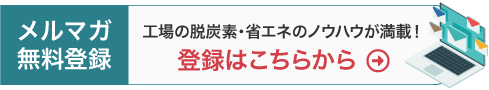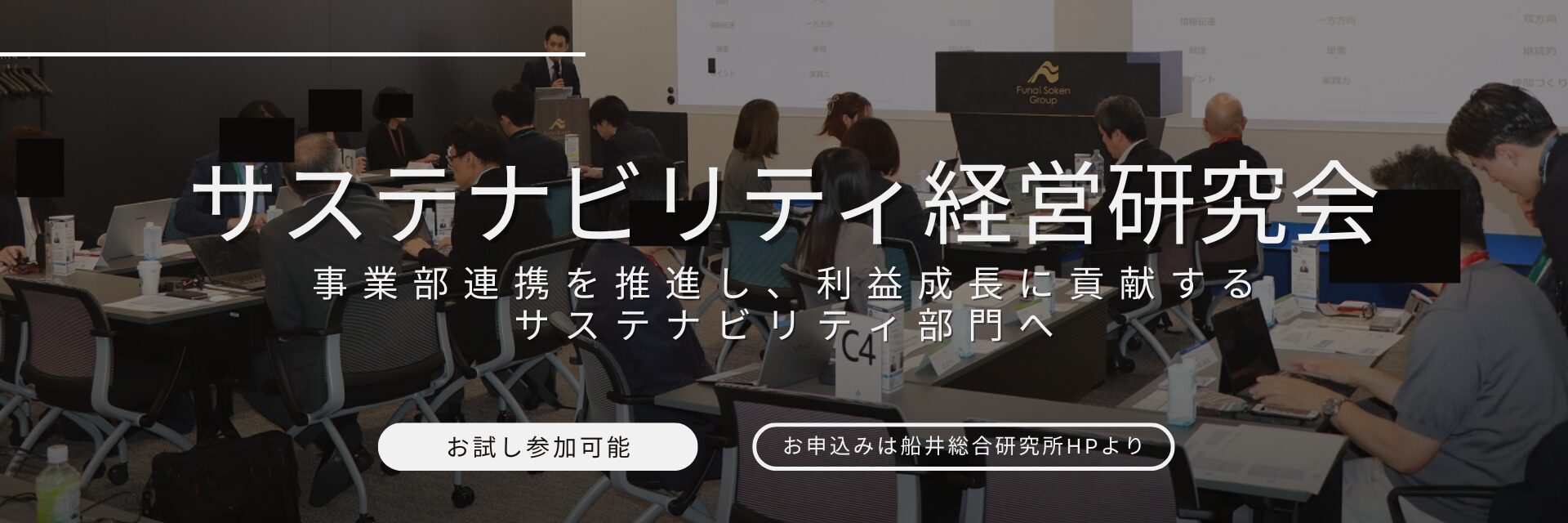サステナビリティ経営研究会 第四回例会「サステナビリティガバナンス」

2025年10月23日に第四回サステナビリティ経営研究会が開催されました。当日は17名の方にご参加いただき、活発な意見交換がなされました。
企業によってサステナビリティ推進の考え方も進捗具合も様々です。当研究会では、そういった同じ目標をもちながらも、異なる視点から情報・意見・事例が出されることで、新たな気づきと示唆を得ることができます。そして、その場で得た気づきをアクションプランとしてお持ち帰りいただき実践することで、各社のサステナビリティ経営が推進していく、そのような場となっています。
第四回例会のテーマ
―――――
サステナビリティガバナンス
①サステナビリティガバナンスとは?監督の場で行われていることとは?
②事業部連携における執行の在り方
―――――
当日の研究会では、「サステナビリティガバナンスとの向き合い方」をテーマに取り上げました。「ガバナンス」と一言で言っても、従来のコーポレート・ガバナンスと、サステナビリティ経営が浸透する現在において、その意味合いは変わってきています。従来のコーポレート・ガバナンスでは、主に株主への説明責任や経営の健全性確保に重点が置かれる傾向がありました。それに対し、サステナビリティ経営が浸透する現在においては、従業員、サプライチェーン、地域社会といった、より広範なステークホルダーの利益や、環境・社会課題への対応を組み込んだガバナンスが求められています。
ガバナンスは監督と執行の2つの側面から成り立ちます。監督側は「方向性の提示」「監視・牽制機能の実効性」「透明性と説明責任」が求められ、執行側には「(戦略実行の)効率性・迅速性」「実効性」が求められます。本研究会はサステナビリティ部門における責任者の方にお集まりいただいており、執行サイドの意思決定者の方々が大半となります。その立場において、いかに監督側に影響を与え、サステナビリティ戦略の執行を効率的・実効性のある形で実現するかが主題となりました。
各講座のご紹介
第一講座 サステナビリティガバナンスの時流解説-サステナビリティ部門責任者に求められるスキルとマインド-
株式会社船井総研ホールディングス サステナビリティ推進室 シニアマネージャー 山路 祐一、スペシャリスト 松永律子

―――――
第一講座では、サステナビリティガバナンスの全体像と、監督側において現在どのような議論がなされているかについて、船井総研ホールディングスの事例を基に山路より解説がなされました。2025年4月30日に公表された『「稼ぐ力」を強化する取締役会5原則』に示されるよう、監督側にはより明確な指針の打ち出しが求められています。事業だけに焦点が当たっている状態のガバナンスは比較的理解しやすい一方、サステナビリティという観点が含まれると、その全体像を把握しづらくなる傾向があります。
また、山路自身は、船井総研ホールディングスにおいてサステナビリティ推進責任者という役割に加え、ガバナンス委員会の事務局も兼任しています。その委員会において監督側がどのような議論をしているかを間近で見る中で、サステナビリティと事業の統合に関する考え方を、サステナビリティ推進側も深く知るべきであると述べられました。
その後、船井総研ホールディングスの松永からは、サステナビリティ部門として監督側・執行側とどのように向き合っているかが紹介されました。船井総研ホールディングスでは「やることはすべてやり切ろう」というトップからの指針が出るに至っています。この指針が示される背景には、サステナビリティ推進部門による、監督サイドのモチベーション向上施策や、執行サイド(他事業部)との連携強化に向けた継続的な働き掛けが存在します。どのように監督サイドの理解を得るか、また、執行サイドとして他事業部とどのように連携しているかといった具体的な事例が共有されました。
第一講座の後には情報交換会・ディスカッションの時間が設けられ、参加者は自社におけるサステナビリティガバナンスの在り方について振り返りを行いました。組織体制には各社の独自性が見られ、その体制を比較分析することが、各社のサステナビリティに対する基本的な考え方や姿勢を把握する上で有用な観点である、との意見も共有されました。
第二講座 営業主体のサステナビリティ推進委員会へ改革した全プロセス
兼松株式会社 企画部サステナビリティ推進室 室長 池田秀子氏

―――――
ゲスト講演では、兼松株式会社 サステナビリティ推進室長 池田氏に、同社にて推進されているサステナビリティ経営の執行強化に向けた取り組みをご講演いただきました。同社では、コーポレートサイドが主体で進めてきたサステナビリティ委員会を、執行力を高めることを目的に、各事業部責任者が参加する場へと変革しました。また、会社の制度としてサステナビリティ項目を組み込むことで、「取り組むことが望ましい」から「取り組むべき必須事項」へと昇華させるに至りました。
このような執行体制の強化を背景として、同社のサステナビリティ指針や取り組みは、一つ一つに会社としての方針が明確に反映されています。例えば、野心的な目標が求められる事項であっても、自社の事業との関連性を踏まえ、取り組むことの必要性を判断されています。そのような積み重ねが、同社の実効性のあるサステナビリティ経営に繋がっています。
第二講座の後の情報交換会では、サステナビリティ推進部門と事業部門との連携、その為の仕組み化・制度化という点で情報交換が行われました。幾つかのグループからは、マテリアリティの再構築を検討・推進している、という意見が聞かれました。最初のマテリアリティが設定されてから3年~5年が経ったことも背景にありますが、それ以上に、事業部と一緒に納得感のあるマテリアリティにすべきという考えから再構築を検討している声が聞かれました。
第三講座 研究会で目指すサステナビリティ部門の未来
株式会社 船井総合研究所 サステナビリティコンサルティングチーム ディレクター 貴船隆宣

―――――
第三講座では、当日のまとめとして、船井総合研究所貴船より講演をしました。戦略的サステナビリティはリスク対応から競争優位へとテーマにおいて、今までの「サステナビリティ=コスト」という考え方から脱する必要性と、その為の考え方として共通価値の創造(CSV)への取り組みということを挙げています。
それが言葉で表されているものとして提示されたのが「マテリアリティは正しいのか」という問いです。本来、PMVV・中計と一貫性を持たなければならないマテリアリティですが、自社のものがそうなっているかというとそうではないといったケースが多くあると言います。
また、事業成長に貢献するサステナビリティ部門となるためには、その実効性が組織設計にあるとしています。当日は、部門間の連携を推進するための理想的な組織設計について解説があり、ご参加企業の皆様には、自社の現状と比較しながら、今後のアクションをご検討いただく良い機会となったかと存じます。
情報交換会の様子と参加企業様のお声




・とても気付きがある回でした。兼松池田さんのお話はサス担としてあらためて覚悟を持つきっかけになると感じました。(建設業 マネージャー職)
・ちょうどマテリアリティの見直し中のため、参考になる学びが多かった。また、情報交換会で非常に興味深い事例を聞くことができた。(製造業 主任級)
・実際と他社との交流ができ、悩みを相談する場にもあり大変ありがたい機会をいただけました。(卸売業 マネージャー職)