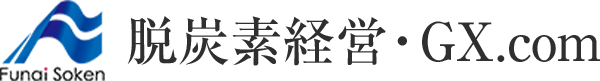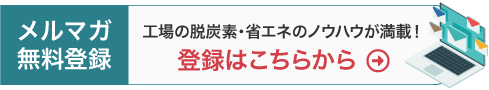サプライヤーエンゲージメント②GHG算定における一次データの活用方法について

前回のコラムでは、多くの企業でサプライヤーエンゲージメントへの取組みが注目されていることをお伝えしました。その背景には、GHG排出量算定においてサプライチェーン全体を対象とする「Scope3」の存在が大きく影響しています。
これは、元から脱炭素においてサプライチェーンの力が機能するように設計されている背景があります。例えば、SBTにおいては、Scope3Cat1の削減目標を設定する場合、サプライチェーンの上流側企業に対して、削減要請を出さなければ、目標達成に至りません。
しかし、従来の二次データ(活動量 × 排出原単位)を用いた算定方法では、サプライヤー個々の削減努力を正確に反映できません。事業成長を目指す企業にとって活動量の増加は避けられず、結果としてGHG排出量が増加し続け、サプライヤーの努力が数値として現れないという課題がありました。
この課題を解決し、実効性のある削減を進める鍵が「一次データ」によるGHG算定・開示です。今回は、一次データを活用した具体的な開示方法について解説します。
1.避けては通れないScope3の削減
地球温暖化対策は喫緊の課題であり、多くの企業が2050年カーボンニュートラルの実現に向けて脱炭素化に取り組んでいます。GHG排出量のうち、Scope3排出量が占める割合は圧倒的に多いと報告されています。
TCFD、ISSB、SSBJ、CDPといった国際的な開示基準や評価フレームワークがScope3排出量の開示を義務化・推奨しており、投資家や取引先からの要求も高まっています。日本政府もバリューチェーン全体の脱炭素化を掲げており、Scope3の削減は、今や避けては通れない最重要の経営課題です。
2.Scope3削減の鍵を握るサプライヤーとの連携
この課題に対し、自社だけでは対応しきれない領域があることをご理解いただく必要があります。Scope3排出量は、事業者自ら排出するScope1、他社から供給される電力等のScope2以外の、事業活動に関連する他社の間接排出を指します。Scope1やScope2は自社で直接的な削減対策が可能ですが、Scope3の多くは自社の管轄外の活動から発生するため、自社努力だけでは削減に限界があります。そのため、Scope3排出量の削減には、サプライヤーや顧客企業といったバリューチェーンパートナーとの連携、すなわち「サプライヤーエンゲージメント」が不可欠です。
これまでの一般的な算定方法である業界平均値等を用いた二次データでは、サプライヤー個々の削減努力が排出量に反映されず、活動量を減らす以外に削減が困難でした。これにより、サプライチェーン全体の脱炭素化を加速させるインセンティブが働きにくいという課題がありました。
仮に、サプライチェーン上の企業に削減要請を出しても、自社が成長していく中ではGHG排出量が増えていってしまうという意図していた結果とは異なるものとなってしまいます。
3.一次データ入手の壁
サプライヤーエンゲージメントを通じてScope3排出量の削減を実効的に進めるには、個々のサプライヤーの活動実態を反映する「一次データ」の活用が不可欠です。一次データとは、GHGプロトコルにおいて「企業バリューチェーン内の固有活動からのデータ」と定義され、サプライヤーから直接提供される排出量データが該当します。
この、サプライヤーから直接提供される排出量データが何を指しているかが、非常に重要なこととなります。製品固有の排出量となるとCFP(Carbon Footprint of Products)となるのですが、CFPの開示を求めるというのは非常に難しく、また、自社自体でもCDPを算定するのは困難極まりないものです。更にその妥当性を示す第三者保証を取得するとなると、それに要する費用は莫大なものとなります。
また、サプライヤー側で排出量算定自体が未実施であることや、算定に必要な知識やリソースの不足、さらに提供データが企業秘密に当たる可能性への懸念、そしてCFP算定の複雑さなどが挙げられます。
つまり、サプライヤーから製品単位での詳細な排出量データ(CFP等)を直接入手することは、現状では困難な場合が多いのが実情です。
4.サプライヤーの開示情報を「一次データ」として活用する新手法
そのような中で、環境省が2025年3月に示した「1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド」は非常に示唆に富むものとなります。これは、一次データの取得に関して、有効な手法を示しています。
・GHGプロトコルにおける一次データの定義
GHGプロトコルでは「企業バリューチェーン内の固有活動からのデータ」、すなわちサプライヤーからの直接排出量データに関して、サプライヤーが自身の算定に二次データを用いていても、一次サプライヤーから提供されたデータは、算定事業者にとって「一次データ」と定義される点としています。(これにより、個々のサプライヤーの活動実態や削減努力を算定に反映させることが可能となります。)
・環境省が示す一次データの一つは「組織ベース排出量データ」
実務上、最も現実的な方法は「組織ベース排出量データ」の活用です。これは、サプライヤーの企業レベルで算定されたScope1,2およびScope3の上流カテゴリ(原則としてカテゴリ1~8)の排出量データを一次データとして受領することを指します。
この際、算定バウンダリは自社のScope3カテゴリ1の対象範囲に合わせ、「Cradle-to-Gate」(原材料調達から生産まで)のデータであることが前提となります。製品ベースの算定に近づけるため、サプライヤーのScope3排出量のうち、カテゴリ2(資本財)、6(出張)、7(雇用者の通勤)、8(リース資産(上流))を除外することも有効としています。(これらのカテゴリは製品に直接紐づかない間接的な排出であるためです。)
受領した組織レベルの排出量は、自社からの購入金額とサプライヤーの総売上高の比率で配分することで、自社に帰属する排出量を算出します。この方法により、サプライヤーの個々の削減努力を自社のScope3排出量に反映させ、バリューチェーン全体の脱炭素化を加速させることができます。
5.一次データ活用がサプライヤーエンゲージメントを加速する
本稿で解説した「組織ベース排出量データ」の活用は、サプライヤーエンゲージメントを具体的な成果に繋げるための現実的な第一歩です。サプライヤーに対し、Scope3まで含めたGHG排出量の算定と開示を依頼することが、エンゲージメントの始まりとなります。
近年、取引先にSBT取得を要請する企業が増えているのも、この流れの一環です。これは、科学的根拠に基づく削減目標の達成をサプライヤーに求めることで、自社のScope3削減を確実なものにしようという戦略的な動きと言えます。
裏を返せば、GHG排出量の開示ができない企業との取引は、自社の脱炭素経営におけるリスクとなり得る時代になったのです。
6.船井総合研究所のGHG Scope3削減支援
サプライヤーエンゲージメントは、時に自社とサプライヤーの利害が相反し、従来の取引関係の延長線上だけでは答えが見つからない難しい課題でもあります。
船井総合研究所では、こうしたScope3削減に関する課題に対し、サプライチェーンにおける削減ポテンシャルの分析から、対象企業へのGHG算定・削減支援、そして貴社の排出量削減の実現までを一貫してご支援します。
気候変動対応を、コストではなく未来への成長の原動力に変えることこそ、サステナビリティ推進に課せられた役割です。この重要なミッションの実現に向け、ぜひ我々にご相談ください。
▼無料経営相談はコチラ▼