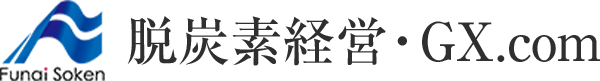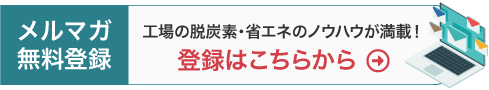サプライヤーエンゲージメント③取り組みを進める企業の動向

ここまでにサプライヤーエンゲージメントの取り組みの重要性について、解説をしてきました。今回は、実際に取り組んでいる企業の動向を踏まえて、どのような流れで議論が進んでいるのか、そして、自社として何をすべきなのかという点について、見ていきたいと思います。
サプライヤーエンゲージメントを推進するステップ
サプライヤーエンゲージメントを成功に導くためには、戦略的かつ体系的なアプローチが不可欠です。そのプロセスは、一般的に以下のステップで構成されます。
・エンゲージメント方針の検討
・削減目標設定
・エンゲージメント目的の共有
・検討体制の在り方
・エンゲージメント対象の選定
・エンゲージメントのタイムライン設定
・エンゲージメント方針の評価・見直し
これらのステップを進める上で、特に大きな障壁となるのが社内での調整です。例えば、エンゲージメント方針について「どこまで踏み込むべきか」、競合他社や顧客の動向を踏まえ「自社としてどこまで関与すべきか」といった点で、部門間の意見対立が生じるケースは少なくありません。
この議論の本質は、エンゲージメントの「目的」を何に置くかという点にあります。企業としてのサステナビリティ施策は、時に現場の利害と衝突します。例えば、サプライヤーへの新たな要請は、短期的なコスト削減目標を担う調達部門や、製品の利益率維持を責務とする営業部門にとって、業務負担の増加や、サプライヤー側からのコスト増(値上げ要求)に繋がりかねない直接的なリスクとなります。結果として、現場レベルで深刻な懸念や抵抗が生じることは想像に難くありません。
このように、サステナビリティ推進部門が理想的な方針を掲げても、事業部門が持つ現場感覚に根差した懸念が障壁となり、具体的な行動に移せないというジレンマは、多くの企業が直面する実情です。この状況を打開し、サプライヤーエンゲージメントを実質的に推進するためには、部門横断的な検討体制を構築し、その上で経営層がサステナビリティを事業戦略の根幹と位置づける明確な方針を全社に示すことが極めて重要となります。
推進する企業の実態感:できる部分から推進していく流れ
実際にサプライヤーエンゲージメントに取り組んでいる企業の対象選定事例は、前述したサステナビリティ推進と事業側のジレンマが表されており、参考になる点が多くあります。多くの企業が、自社のサプライチェーン排出量のうち、排出量の多い主要カテゴリー(特にScope3のカテゴリ1:購入した物品・サービス)に該当するサプライヤーを優先的な対象としています。それに加え、取引先との関係性の深さや、脱炭素への取り組みに対する意欲の高さを考慮するケースが多く見られます。
・総合建設コンサルティング(東証プライム上場):Scope3 Cat1における取引関係が高く意欲ある取引先
・流通業(東証プライム上場):Scope3 Cat1のペットボトル飲料に該当し、かつリサイクルの取り組みで連携していた取引先
・サービス業(東証プライム上場):Scope3 Cat1における取引関係が高く意欲ある取引先
・工作機械メーカー(東証プライム上場): Scope3 Cat1において取引歴が長い取引先
・流通業(東証プライム上場): 環境配慮に注力したいPB製品を製造する取引先のうち参加意欲の高い取引先。
・建材メーカー(未上場):同社が提供する削減効果の大きい低炭素建材を使用し、バイオマス燃料への転換を計画している道路舗装会社や、バイオマス燃料供給を担う団体
これらの事例から、多くの企業がやみくもに全サプライヤーに働きかけるのではなく、影響度や実現可能性を考慮して戦略的に対象を選定していることが分かります。
プライム・グローバル企業から取り組みは進む、要請対応の準備は必須
現在のサプライヤーエンゲージメントは、主にプライム市場の上場企業、特に時価総額の大きい企業や、欧州系および欧州向けに製品を輸出している企業からの要請が中心です。これらの企業は、自社のScope3排出量削減目標達成のため、取引先へのデータ提出や削減協力の働きかけを開始しています。具体的には、CO2排出量の算定データ提出依頼や、SBT(Science Based Targets)などの削減目標設定の要請、脱炭素への取り組みに関するアンケート調査などが実施されています。
一方、非上場企業においては、まだサプライヤーエンゲージメントに自社から積極的に取り組む必要性は薄いかもしれません。しかし、前述のような大手企業や欧州系顧客からの要請を受ける可能性を考慮すると、要請を前提としたScope3排出量の算定準備は急ぐ必要があります。現時点では、サプライヤーに対して詳細なデータ提出を求める段階にない場合でも、自社のScope3排出量をある程度把握しておくことは、将来的な要請への対応力に直結します。Scope3の算定には、一次データ(取引先からの直接データ)が理想ですが、導入期においては、環境省・経産省等が提供する「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」や、排出原単位データベースが公開されている「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」などを活用した二次データでの算定でも十分と考えられます。
第一歩目としてWEBにおける情報開示から
サステナビリティに関する取り組みは、「攻め(機会の創出)」と「守り(リスクの低減)」の双方の視点を持つことが重要です。特に、サプライヤーエンゲージメントという領域は多くの企業にとって「導入期」であるため、「攻め」と「守り」が表裏一体となっています。早期に着手すること自体が、取引関係という事業基盤を「守り」、同時に顧客から選ばれる要因、すなわち「攻め」の姿勢にも繋がるのです。
サプライヤーエンゲージメントについては、超大手企業であってもまだ手探りの状態であり、サプライチェーン全体を巻き込んだ本格的な取り組みができている企業は多くありません。この状況は、裏を返せば、早期に取り組むことで競争優位を築く大きなチャンスがあることを意味します。大手顧客からの脱炭素要請に迅速かつ的確に対応できるサプライヤーは、取引先にとって代替の難しい、価値の高いパートナーとして認識されるでしょう。
更に、SBT認定を取得するなど、脱炭素への具体的な目標と行動を客観的に示すことができれば、競合他社との明確な差別化が可能です。これは、新たな取引の獲得や既存取引の強化といった「攻め」の経営に直結します。
また、Webサイト等でのサステナビリティ情報の開示も、導入期に実施すべき重要なアクションです。上場企業のような法的な開示義務がない非上場企業であっても、自社の環境への取り組みやScope3に関する情報を積極的に開示することで、顧客や金融機関といったステークホルダーからの信頼を高めることができます。まずは発信できる情報からでも、Webサイト等を活用して戦略的に情報発信を始めることを強く推奨いたします。