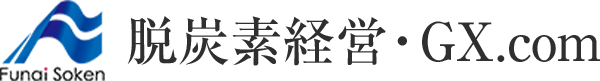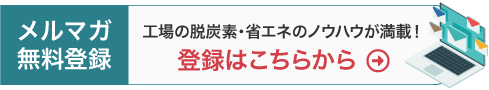事業とサステナビリティを結びつけるマテリアリティ構築①
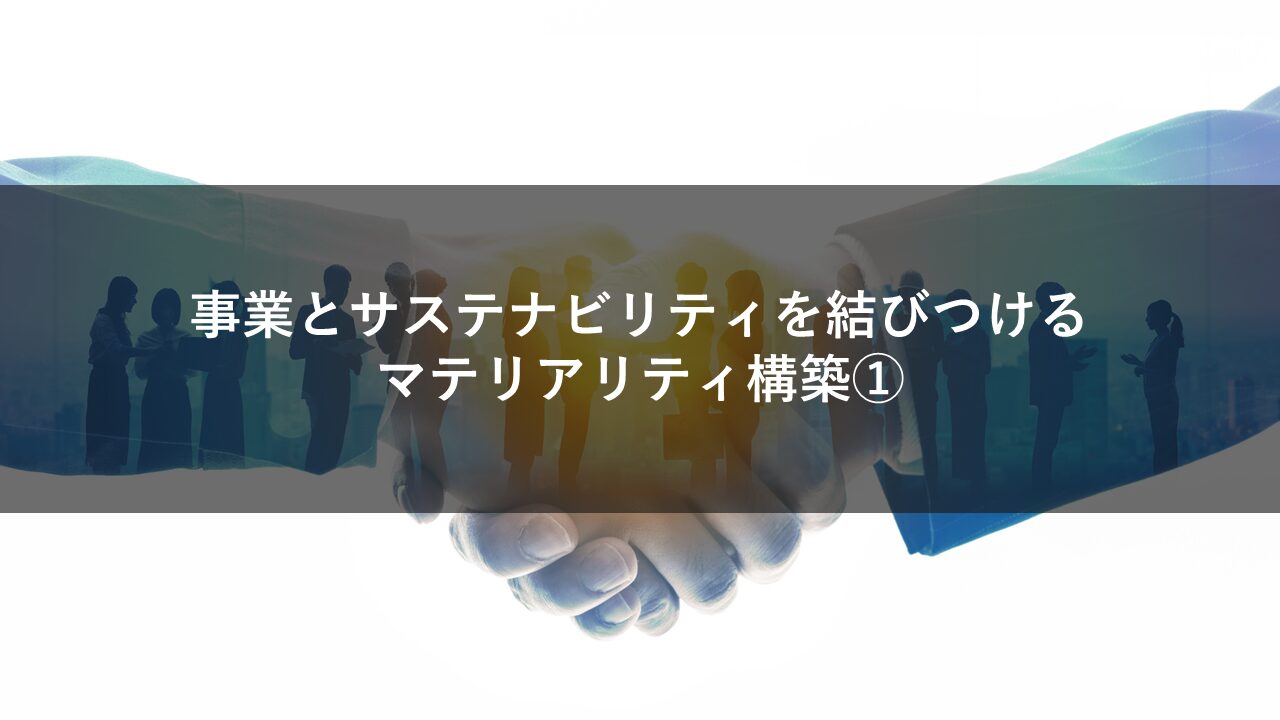
サステナビリティ経営の重要性を耳にする機会は増えていますが、多くの推進現場において「取り組みがコスト先行になっている」「事業成長との繋がりが見えない」といった課題から、推進が停滞しているという声が聞かれるのも事実です。確かに、サステナビリティの追求のみを絶対的な目的として捉えれば、事業活動と両立しない場面が大半と言えるでしょう。
しかし、どのような事業も、元をたどれば顧客や社会の「課題解決」から始まっているはずです。その原点に立ち返れば、事業活動とサステナビリティは決して対立するものではありません。ではなぜ、両立が難しく感じるのでしょうか。それは、短期的な数値目標を追う事業部門と、長期的な視点で社会課題を見るサステナビリティ部門とで、視界が異なっているためです。本質的に問われているのは、これら二つの視点を統合し、事業の根幹とサステナビリティをどう結びつけるかという点に他なりません。
昨今、外部環境の不確実性は増す一方です。例えば、米国の政権交代の可能性が示唆されるように、国際的な潮流がいつ変化するか予測困難な状況下では、ただ「要請されるからやる」という受け身の姿勢では、変化の波に翻弄されるだけでなく、取り組みの意義そのものを見失いかねません。今まさに、「自社にとって本当にやる意味のあることは何か」を見極め、そこに経営資源を集中させることが求められています。
そこで羅針盤となるのが、自社の事業活動とサステナビリティを結びつける「マテリアリティ(重要課題)」の特定です。3回に分けて、このマテリアリティについて考察を深めていきたいと思います。
第一回の目的:マテリアリティとは何なのかを理解する
最初のテーマは、マテリアリティとは何なのか、どういった背景で重要であるといわれているのかについて、解説をしていきます。この問いを解き明かすため、まずはサステナビリティ経営の土台となる「ESG」の重要性、そして事業と社会価値を両立させる「CSV経営」の考え方を整理します。その上で、なぜ数ある取り組みの中から「マテリアリティ」にフォーカスすることが、不確実な時代の羅針盤となるのかを解説していきます。
ESGの歴史と事業とサステナビリティの関係性
企業の社会に対する関わり方として、ESGよりも先に表された言葉が「CSR:企業の社会的責任」です。この段階では、事業で得た利益の一部を寄付や環境保護活動といった形で社会に還元するという、いわば事業活動とは切り離された慈善活動としての側面が強いものでした。しかし、気候変動や人権問題といった地球規模の課題が深刻化するにつれ、それらが企業の事業活動と決して無関係ではないことが明らかになっていきます。
この流れを決定づけたのが、2006年に国連が提唱した「PRI(責任投資原則)」です。ここでは、投資家が投資先を選定する際に、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの観点、すなわち「ESG」を考慮することが求められました。これは、企業の非財務情報であるESGへの取り組みが、企業の長期的なリスク耐性や収益機会、ひいては企業価値そのものに直結するという考え方に基づいています。
このESGというフレームワークの登場により、サステナビリティは「事業の外にある慈善活動」から、「事業の根幹に関わる経営課題」へとその位置づけを変えようとしています。例えば、気候変動は自然災害によるサプライチェーンの寸断(リスク)だけでなく、新たな省エネ技術や再生可能エネルギー市場の創出(機会)にも繋がります 。つまり、ESGは企業経営を行っていく上で欠くことができない視点であるということを示したのです。
CSV経営の潮流
ESGという視点が「サステナビリティは事業の根幹に関わる経営課題である」と明確にしたことで、企業経営には次なる問いが生まれました。それは、「では、企業はどのようにして事業活動を通じて社会課題の解決に取り組むべきか?」という、より実践的な問いです。
その戦略的アプローチとして大きな潮流となったのが、「CSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)」という経営理念です。
従来のCSRが「事業で得た利益を社会に還元する」というコストとしての側面を持っていたのに対し、CSVは「社会課題の解決そのものを事業機会と捉え、経済的価値と社会的価値を同時に追求する」という点に本質的な違いがあります。つまり、社会課題を事業のリスク要因としてではなく、機会として取り込むことで、新たな事業展開や競争優位性を生み出すことを目指すことを指しています。
このCSVが提唱されたのは、ハーバード大学経営学科のマイケル・ポーター教授と同ケネディスクールのFSG共同創設者であるマーク・R・クレイマー氏によって執筆された2011年1月「共有価値の創造:資本主義と社会における企業の役割の再定義」という記事によるものです。
CSVとしばしば比較されるCSRですが、その思想の成り立ちは大きく異なります。CSRは、企業の経済成長に伴い顕在化した倫理的課題などに対し、その解決をCSRという言葉で両者を統合しようとした考え方であるといえます。その結果、企業経営の最大の目的は、企業と社会のバランスが取れた成長を目指すものとされるようになります。ある論文において、CSRには4つの段階があるとされ(第一段階:経済責任/第二段階:法的責任/第三段階:倫理的責任/第四段階:慈善的責任)、その内容からもCSRは企業の経済成長と社会課題の解決に向けたアプローチを別と考えている様子が見て取れます。
一方、CSVの考え方はCSRとは異なります。CSRが経済的成長と社会課題の解決を別のものと捉えるのに対し、CSVは企業活動そのものが社会的価値の創造と経済的利益の追求を同時に実現するものと考えます。さらに、その視点で取り組むことは、周辺コミュニティを巻き込んだ活性化に繋がり、結果として企業自身の競争力も強化されるとしています。
その具体的な競争力強化の方法論として3つの方法が用いられるとされています。
1.製品・市場の再定義
社会課題をベースとした、新たな市場への参入・既存市場への新製品の投入をすることで社会性・経済性双方の成長を実現できる可能性がある
2.バリューチェーンにおける生産性の再定義
バリューチェーン全体で管理をすることで、資源利用や生産性の再定義をすることで製造コストを落とすことを通して競争優位性を獲得することができる
3.事業拠点を置く地域での産業クラスター形成
周囲の環境と共に成長することで、安定した成長をすることができる
このCSV経営を実践していく上で、「数ある社会課題の中から、自社の事業にとってどの課題に取り組むことが、最も大きな共通価値の創造に繋がるのか?」という問いに答える、つまり取り組むべき優先課題を見極めるプロセスが不可欠となります。そして、その羅針盤となるのが、次にお話しする「マテリアリティ」の考え方です。
マテリアリティとは何か?
CSV経営を実践していく上で、「自社の経済的成長と社会課題の解決の双方が両立する事業とは何か?」という問いに答える、つまり取り組むべき優先課題を見極めるプロセスが不可欠となります。この「企業にとっての重要課題」こそが「マテリアリティ」です。
一つ重要な視点として、マテリアリティはあくまで事業と社会課題が交差する領域における重要課題を指しているということを挙げます。企業の第一義的な目的が経済成長であることは言うまでもなく、世の中の全ての社会課題に企業が直接取り組むことが常に最適解とは限りません。企業が本業で利益を上げ、その結果として納税という形で社会に資金を還元することも、極めて重要かつ正当な社会貢献の形です。
その上で、あえて「マテリアリティ」を特定する必要があるのか。それは、自社事業の強みと社会課題解決の双方が実現するテーマこそ、新たな事業機会や競争優位性の獲得を通した企業自身の持続的な成長に繋がる領域であり、それを見つけ出すための戦略的なプロセスだからに他なりません。
つまり、マテリアリティの特定とは、自社の持続的成長領域を見出すための手法と言えます。では、このマテリアリティを具体的にどのように特定していけばよいのでしょうか。次回からは、その実践的なプロセスについて詳しく解説していきます。