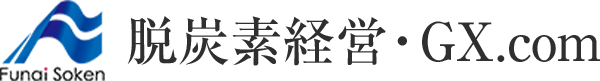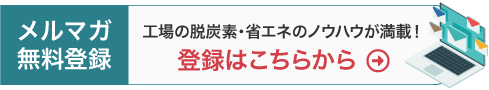事業とサステナビリティを結びつけるマテリアリティ構築②
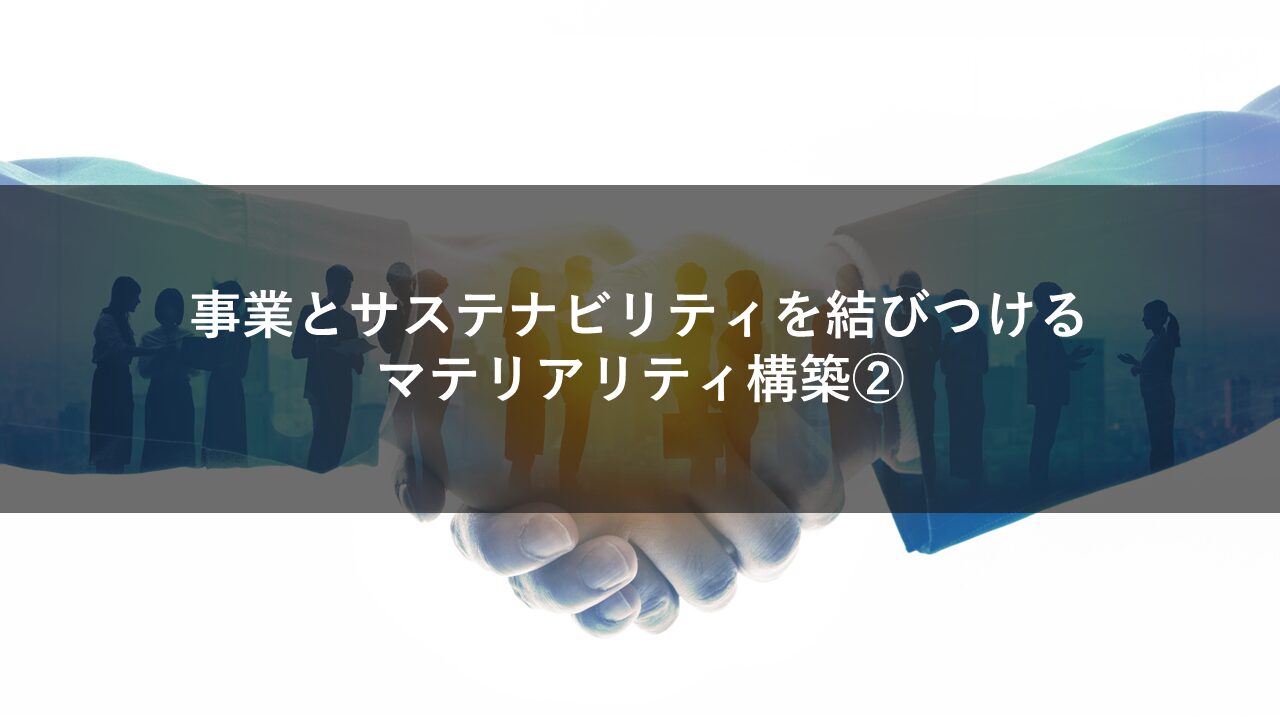
第一回目のコラムでは、マテリアリティの前段階としてESGの歴史、CSV経営の重要性とマテリアリティの立ち位置についてお伝えしました。特にCSVは、社会課題の解決と事業成長を両立させることで競争優位性を獲得するという、非常に意義深い経営アプローチです。その背景には、バリューチェーン全体の生産性の再定義、事業拠点である地域社会との共存共栄、そして製品・市場自体の再定義といった視点が含まれています。そして、この社会課題と事業成長が交わる領域を見出すためのプロセスこそが、マテリアリティ特定に他ならないと述べました。
第二回となる今回は、そのマテリアリティの具体的な特定プロセスについて解説します。
第二回の目的:形骸化させない「機能するマテリアリティ」の作り方
多くの企業が「マテリアリティ」を策定している一方で、「策定したものの形骸化している」「サステナビリティ推進担当者だけの目標になっている」といった課題も聞かれます。また、これらは上場企業だけの課題だと捉えている中堅・中小企業の経営者様もいらっしゃるかもしれません。この「マテリアリティ」は持続的成長を実現させたいと考えている企業であれば、すべての企業が一度は検討・議論をすべき事項であるといえます。その上で本稿では、「機能するマテリアリティ」をいかにして作るか、という点に焦点を当て、具体的に解説します。
「機能するマテリアリティ」とは何か?
各企業のマテリアリティを見ていくと、様々に思考を凝らした結果であると感じられます。そこにかける想いは、大きなものであると考えますが、今回はその中でも「機能するマテリアリティ」とは何かという点について考察します。
ここで言う「機能する」とは、マテリアリティが起点となり、企業経営に具体的な影響を与えている状況を指します。その設定背景からも、事業成長と社会課題解決の双方に貢献することは自明です。マテリアリティには、その進捗を測るためのKPIを設定するのが通例であり、そのKPI群には事業成長と社会課題解決、両者の観点が含まれていることが求められます。
では、具体的にどのような影響を与えうるのか、3つの観点から要点を挙げます。
一つ目は、「事業戦略策定において示唆を提示する情報を有する」ことです。マテリアリティを構築する過程は後述しますが、その過程において将来の事業環境におけるリスクと機会を網羅的に把握することとなります。これは、既存の事業計画に後からサステナビリティの要素を加えるといった対症療法的なアプローチではありません。むしろ、現在の事業の延長線上に潜むリスクや、新たな事業機会といった「重要な示唆」を経営層に与え、戦略議論の質を高めるきっかけとなるものです。
エシカル消費といったこれから顕在化するだろうニーズに対する市場参入するヒントになることや、炭素税を始めとする未来の規制に対するリスクヘッジといった、TCFD提言対応といった既知の取組に限らず、例えば、多様な価値観を受け入れることで自社製品のデザインや機能に新たな視点を付加するなどといったことも含まれます。※これは、DE&I(「Diversity(多様性)」「Equity(公平性)」「Inclusion(包括性)」という人的資本経営のポイントとなる考え方)という社会課題への取り組みを機会として向き合うことで生まれる視点です。この視点から、自社における多様性の受け入れ方について、取り込むべき要件などを明確にすることができます。
二つ目に、「責任の所在が明確である」ことです。マテリアリティは全社的な目標として認識されがちですが、その実効性は事業部門や機能部門単位での運用にかかっています。それぞれの課題に対し、最もコミットすべき部門や担当役員の存在は不可欠です。テーマごとに執行役員や部長クラスの執行責任者が明確化され、そのリーダーシップのもとで活動が推進されて初めて、マテリアリティは実効性を持ちます。
三つ目は、「KPIと事業目標が連動している」ことです。新たにサステナビリティに関するKPIを設定するだけでなく、各事業部門が日々の業務で既に追求している既存のKPI(例:コスト削減率、生産性向上率など)が、いかに社会課題の解決に貢献しているかを明確に紐づけることが極めて重要です。この紐付けにより、マテリアリティへの取り組みが「追加業務」ではなく「本来業務そのもの」として現場に深く浸透していきます。
結論として、「機能するマテリアリティ」とは、サステナビリティという視点を企業戦略に統合し、社会課題への対応と企業の持続的成長を両立させるための戦略的なツールと言えます。決してサステナビリティという個別要素を最優先するのではなく、企業が変化の激しい時代を勝ち抜くための一つの重要な羅針盤として捉える視点が肝要です。
マテリアリティの構築プロセス
「機能するマテリアリティ」のゴールが明確になったところで、次はその具体的な作成プロセスを見ていきます。ここでは、社会課題の洗い出しから、自社が取り組むべき重要課題を特定するまでの一連の流れを、大きく3つのステップに分けて解説します。
Step1:自社と環境・社会の「接点」を洗い出す「バリューチェーン分析」
最初に行うのは、自社の事業活動が「どこで」社会や環境と関わっているのかを網羅的に可視化することです。そのための有効な手法が「バリューチェーン分析」です。原材料の調達、製造、輸送、販売、そして製品が使用され廃棄されるまで、事業の各段階において、環境・社会にどのように依存し、また、どのような影響を与えているかを客観的に整理していきます。
例えば、製造業であれば「調達」段階ではサプライヤーの人権問題や生物多様性、「製造」段階ではエネルギー消費や水使用、労働安全衛生、「使用」段階では製品の省エネ性能などが接点として挙げられます。この洗い出しを丁寧に行うことが、次のステップの土台となります。
Step2:接点から「リスク」と「機会」を特定
Step1で可視化した「接点」に対し、気候変動や人権、法規制、技術革新といった世の中のトレンドや社会課題を掛け合わせていきます。この時にSDGsやGRI、SASBといった国際的なフレームワークを参照しながら、自社に関連する課題を網羅的に特定します。ただし、これらは膨大な情報量を含むため、まずは大項目レベルで自社との関連性を認識し、環境・社会への依存度や影響度が大きい領域から詳細を分析していくと効率的です。
具体的な項目を以下にピックアップしてみましたので、是非ご参考ください。
環境 (Environment)
気候変動とエネルギー/資源循環と汚染防止/水資源と生物多様性
社会 (Social)
人権と労働慣行/安全衛生とウェルビーイング/多様性、公平性、インクルージョン(DEI)と人材育成/
製品・サービスの責任/顧客情報保護とデータセキュリティ/地域社会との関係
ガバナンスと経済 (Governance & Economic)
コーポレート・ガバナンスと倫理/持続可能なサプライチェーン・マネジメント/リスク管理と事業継続性/イノベーションと機会創出
これらの事項を踏まえ、リスクと機会を紐づけていきますが、そのアプローチには大きく2つの観点があります。
一つは、リスクの裏側に機会を見出す視点です。事業を取り巻くリスクは、業界共通の課題であることが少なくありません。つまり、他社も同様に認識しているリスクを、自社の技術やノウハウで解決し競争力の源泉へと転換できれば、それは大きな事業機会となり得ます。
もう一つは、CSV(共通価値の創造)の観点から、積極的に機会を創出するアプローチです。これは、社会課題の解決と企業の経済的利益を両立させる考え方で、特に「①製品・市場の再定義」「②バリューチェーンの生産性の再定義」「③地域における産業クラスターの創出」という3つの視点(前回のコラム参照)が、新たな機会を発見する上で有効です。
まずは、これらの方法を用いて、短期・中期・長期の時間軸も意識しながらリスクと機会を一覧化していきます。
Step3:「ダブルマテリアリティ」の視点で優先順位を決める
Step2で洗い出した多数のリスクと機会の中から、自社が優先的に取り組むべき課題を絞り込みます。その評価軸となるのが、「ダブルマテリアリティ」の考え方です。これは、以下の2つの視点から重要性を評価するアプローチを指します。
財務的マテリアリティ(企業への影響):
その課題が、企業の財務(売上、コスト、資金調達など)に与える影響は大きいか?
インパクトマテリアリティ(社会への影響):
その課題に対し、自社の事業活動が社会や環境に与える影響は大きいか?
この2つの軸で評価を行い、双方、もしくはいずれかにおいて特に重要と判断されたものが、自社が取り組むべき「マテリアリティ」となります。このプロセスを経ることで、社会的な要請に応えつつ、自社の企業価値向上にも資する、戦略的な重要課題を特定することができます。
多くの企業では、この分析を経て3~7つ程度の課題をマテリアリティとして設定する傾向にありますが、その選定においては、自社と社会・環境の双方に与える影響を常に念頭に置くことが求められます。
そして最後に、特定した重要課題を、社内外のステークホルダーの共感を呼ぶ言葉へと昇華させる「言葉選び」の段階へと入ります。マテリアリティは、自社の未来を創る成長の原動力です。発表した際に、社員一人ひとりが「自社らしさ」を感じ、その実現に向けたモチベーションが湧き上がるような、シンプルかつメッセージ性に富んだ言葉で表現することが最終的なゴールとなります。
今回はマテリアリティを特定するまでの一連のプロセスを解説しました。次回は、この特定したマテリアリティを、いかにして事業部門に落とし込み、KPIを設定し、全社で機能させていくのか、その具体的な仕組み作りについて解説します。