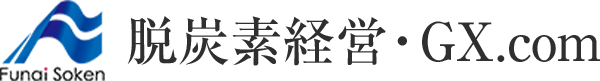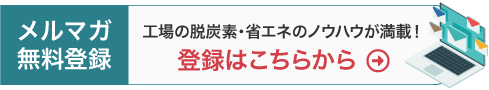事業とサステナビリティを結びつけるマテリアリティ構築③
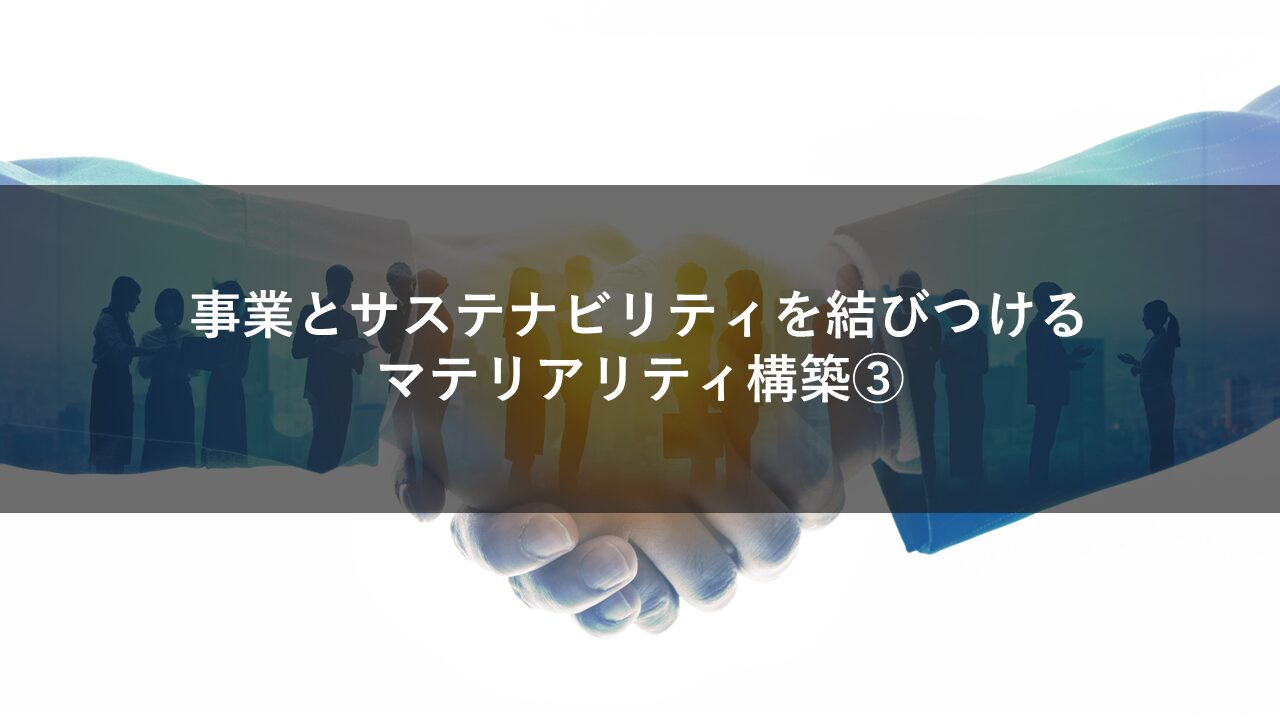
第一回、第二回のコラムを通して、これからの企業経営におけるマテリアリティ策定の重要性についてお伝えしました。第一回コラムではマテリアリティの前段階としてESGの歴史、CSV経営の重要性とマテリアリティの立ち位置までを。第二回のコラムでは、機能するマテリアリティの要素と具体的な策定プロセスまでをご紹介しました。さて、ここまでに策定されたマテリアリティは、自社を未来の成長に向けてエンゲージメントさせる大指針ではありますが、現状ではあくまで方向性を示しているにすぎません。ここから具体的に実行段階へと入っていくのが、最後である本コラムのテーマです。
第三回の目的:マテリアリティを成長の原動力に。実際に機能させる為に。
本シリーズ最後のコラムは、マテリアリティを機能させる為に、どのように仕掛けを作っていくかという点です。その具体的な手法はKPIの設定と、モニタリングによる定点観測、KPI達成のためのアクションを取っていくことになります。
マテリアリティを実際に動かすためのKPI設定
前回で特定したマテリアリティは、いわば自社が進むべき方向性を示した「定性的な方針」です。しかし、方針だけでは具体的なアクションには繋がりません。この方針を全社的な活動へと落とし込むために不可欠なのが、進捗を測るための「定量的な指標(KPI)」の設定です。KPIを設定することで、抽象的だった目標が具体的になり、誰が何をすべきかというアクションが明確になります。そして、その進捗を客観的に管理できるようになることで、マテリアリティ達成への道筋が「見える化」されます。
改めてとなりますが、マテリアリティは事業面と社会・環境面の視点から設定されていることを認識しておくことが必要です。これは、実際には以下のような関係性として見ることができます。
・事業目標を達成するプロセスそのものが、社会・環境課題の解決に貢献する仕組み
・社会・環境課題への取組みが、新たな事業機会やブランド価値向上といった形で事業に還元される仕組み
・事業活動の一環として社会・環境に配慮することが、リスク低減や評判の維持といった形で間接的に事業基盤を強化するインパクトを与えられる
このような、視点でマテリアリティが構築されていることが理想であるといえます。
そのため、このマテリアリティを機能させる為のKPIにも2つの種類があるといえます。
事業KPI: 売上高、利益率、生産性、コスト削減額など、従来から事業活動の成果を測る指標等
社会・環境KPI: CO2排出量、女性管理職比率、再生可能エネルギー使用率、社会や環境への貢献度等
仮に、マテリアリティが事業面と社会・環境面の双方を踏まえて構築されている場合、双方のKPIには何かしらの関係性が生まれていることと考えられます。仮に、マテリアリティが事業面と社会・環境面の双方を踏まえて構築されている場合、双方のKPIには何かしらの関係性が生まれていると考えられます。例えば、ある食品メーカーが「サプライチェーン全体でのフードロス削減」をマテリアリティに掲げたとします。この場合、「フードロス削減率(社会・環境KPI)」を高める活動が、結果として「原材料廃棄コストの削減(事業KPI)」や「サステナブルな企業としてのブランドイメージ向上による売上増(事業KPI)」に繋がります。
この紐付けを社内外に説明できることが、マテリアリティが事業成長に貢献する戦略であることを示す上で非常に重要です。
この時、KPIの目標値をどのように設定するのかという議題へと入っていきますが、特に社会・環境KPIについては、実態を掴みづらいという点から難しく感じる部分でしょう。ここでは、そこに対して、ヒントとなる考え方を2つご提示します。
守りのKPI(コミットメントレベル)
これは、法規制や業界基準への対応など、事業を継続していく上での前提条件を満たすための目標です。
例えば、TCFD提言に沿った情報開示や、サプライチェーンにおける人権デューデリジェンスの実施などがこれにあたります。
業界の誰もが対応を求められるため、これ自体が直接的な競争優位性を生むことは稀です。しかし、その対応の「早さ」と「効率性」は、間接的な競争力に繋がります。他社より早く、低コストで対応できれば、そこで生まれた余力を「攻め」の領域に投資できます。また、世の中の要請に真摯に応えるという自社の姿勢を示す上でも不可欠なKPIです。
攻めのKPI(野心的な目標)
こちらは、新たな市場創造や圧倒的な競争優位性の確立に直結させるための、意欲的な目標です。
例えば、バリューチェーン全体でカーボンニュートラルを達成するという高い目標や、革新的な技術で海洋プラスチック問題の解決に貢献する、といった目標が挙げられます。この目標を設定するには、「なぜ他社に先駆けて取り組むのか」「達成した暁には、どのような圧倒的な成果が得られるのか」という、明確な経営戦略とセットであることが求められます。
野心的な目標は、自社の未来を切り拓くための、強力な成長の原動力となるでしょう。
KPIを用いて自社のサステナビリティ経営を推進する
特定したマテリアリティと、それを測るためのKPI。これらを実効性のある形で機能させることが最後のテーマです。本稿では、そのための重要な2つの仕組み、「事業計画との連動」と「継続的な推進体制」について解説します。
第一に、定めたKPIを事業計画と完全に連動させることが不可欠です。マテリアリティの側面から構築されたKPIと、中期経営計画に組み込まれているKPIが一致していなければ、組織としての歩調が合いません。CSVの考え方が示す通り、サステナビリティと事業は本来両立されるべきですが、現実的には事業計画が優先されがちです。だからこそ、マテリアリティの策定プロセスを通じて明らかになった長期的なリスクや新たな事業機会といった戦略的な示唆を、経営層が未来の舵取りを議論する上での質の高いインプットとして提供することが重要です。まずは経営戦略の羅針盤の一部として機能させることが、全社的な理解を得るための第一歩となるでしょう。
第二に、継続的な運用・改善を担う推進体制を構築することが求められます。マテリアリティへの取り組みが一部署の活動で終わらず、全社的なうねりとなるためには、経営層の強いコミットメントと、全部門を巻き込む推進母体の両輪が不可欠です。
先ず、経営層のコミットメントという点では、マテリアリティの推進責任者をどのように割り振るかという考えも重要になります。マテリアリティ・KPIの推進責任者というとサステナビリティ推進担当というイメージがありますが、本当にそれが適任でしょうか?マテリアリティの考えでは、事業面、社会・環境面の両側面に対して影響するということが前提にありました、場合によっては、事業部門の上位役職者がマテリアリティの達成に向けて動くことが適切な場合もあります。
さらに、その「旗振り役」を支え、実務を動かすために、経営企画、事業部門、人事、IRといった関係部署のキーパーソンから成る部門横断の「サステナビリティ委員会」を設置し、定期的な進捗確認と改善策を議論する場を設けることが重要です。マテリアリティの各項目は独立しているように見えても、実際は複雑に絡み合っています。だからこそ、会社を主導する各機能の代表者が連携し、PDCAサイクルを回しながら推進していくことが、持続的な企業価値向上への理想的な姿と言えます。
―――――
全3回にわたり、マテリアリティの戦略的重要性から、具体的な特定プロセス、そしてKPIと連携した実行体制の構築までを解説してきました。マテリアリティとは、社会からの要請に応えるだけでなく、自社の持続的成長領域を見出すための羅針盤です。本稿が、皆様の会社が未来に向けて力強く舵を切るための一助となれば幸いです。